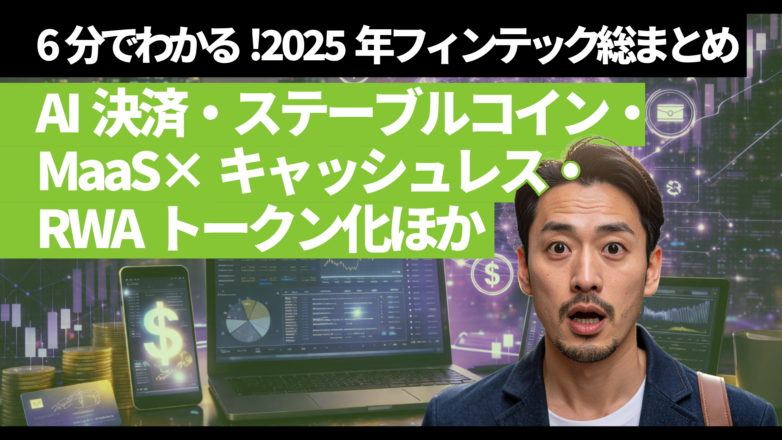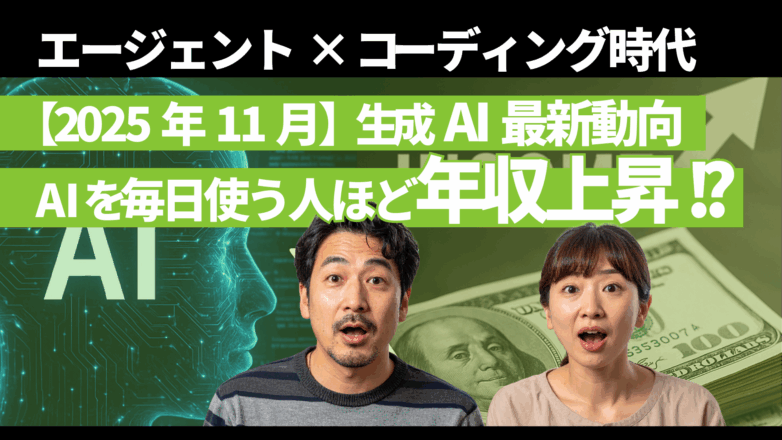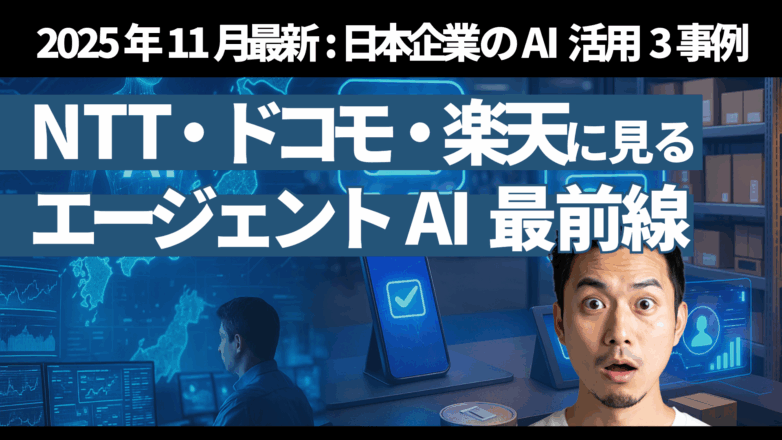目次
1. 2025年の本質:AIは「書く」より「回す」を変える
2024年までの主役は“コード補完・レビュー支援”でしたが、2025年は一段進んで、複数ツールをまたいでタスクを自律的に進めるAIエージェントが現場に入り始めました。GitHubは、観測(Observability)・IaC・セキュリティまで含めてSDLC全体を支えるために、Copilot上で動くカスタムエージェント(Markdownで定義するドメイン専門家)を提示しています。
ポイントは「AIがコードを書く」ではなく、「チームのルール(標準・手順)に沿って、調査→修正→検証→記録までを一気通貫で回す」方向に進んだことです。
詳細記事:COBOLを学ばずにレガシーシステムを近代化!3ステップフレームワーク【GitHub Copilot活用ガイド】
2. 上流工程が変わる:要件・設計は“社内知”が勝敗を分ける
金融のように正確性が求められる領域では、AIに“何を見せるか”が成果を左右します。ソニー銀行×富士通の取り組みでは、開発・テスト領域から生成AI適用を開始し、ナレッジグラフ拡張RAGで入力データを高度化しながら精度を上げる方針が示されています。
これは「一般的なLLM」より、自社の設計情報・過去案件・規約を取り込んだ“現場仕様のAIへ移る流れを象徴します。
詳細記事:生成AIでシステム開発の工数20%短縮へ!ソニー銀行、日立など国内最新事例5選から学ぶ成功の鍵
3. レガシー刷新が現実路線に:COBOLは“学ぶ”より“解く”
2025年の大きな転換点は、レガシー近代化でAIが“補助”を超えたことです。ここで重要なのは「AIが開発者の代わりになるのではなく、能力を拡張する」点だと整理されています。
GitHubは、COBOL経験がない開発者がAIを使い、現場のCOBOL有識者の知見と組み合わせて近代化を進める事例を紹介しています。
さらにMicrosoftの技術ブログでは、Semantic Kernel等を用いたエージェント分担型(解析・変換・依存関係マッピングなど)で、COBOLをクラウド対応Javaへ移行するアプローチを具体的に解説しています。
重要なのは「全部を書き換える」より、①構造理解(依存関係の可視化)→②段階的変換→③検証とログで追跡、という手戻りを最小化する設計です。
詳細記事:COBOLを学ばずにレガシーシステムを近代化!3ステップフレームワーク【GitHub Copilot活用ガイド】
4. テストと運用が伸びしろ:AIは“品質保証の自動化”に効く
AI導入の効果が出やすいのは、実はコーディングよりテスト生成・変更影響分析・運用ナレッジの検索です。上流〜下流がつながるほど、バグの早期発見と手戻り削減が効いてきます。Microsoftのレガシー移行でも、依存関係を分析し図示し、レポートやログとして残す思想が強調されていました。
詳細記事:COBOLを学ばずにレガシーシステムを近代化!3ステップフレームワーク【GitHub Copilot活用ガイド】
5. 人材面の結論:使う人が伸びる。組織は“学びの格差”を埋める
日常的に生成AIを活用する人ほど“年収上昇”の傾向があります。
「AIで仕事が奪われる」より現実的なのは、AIを使える人と使えない人の差です。PwCの調査では、職場で生成AIを“毎日”使う人は、そうでない人に比べて生産性・雇用安定・給与面でのメリットを感じている割合が高い一方、日常的に使っている人は14%に留まるとされています。
つまり2025年の課題は「導入」ではなく、使いこなすための設計(ガイドライン、教育、評価指標)です。
詳細記事:【2025年11月版】生成AIを毎日使う人ほど年収上昇!? エージェント×コーディング時代のAI最新動向
まとめ:2026年で外さない実践チェックリスト(明日からできる)
最後に、ここまでの内容を踏まえて、社内導入を“PoC止まり”にしないための5つのポイントをご紹介します。
- 対象業務を絞る:まずは「設計書作成」「テストケース生成」「変更影響分析」など、成果が測りやすい工程から
- 社内知の整備:規約・設計標準・用語・過去障害のナレッジをRAGで引ける形に
- エージェント運用を前提にする:単発のチャットではなく、調査→修正→検証→記録までの流れをテンプレ化(Copilotのカスタムエージェント発想が参考)
- ガバナンスを最初に置く:機密データの扱い、生成物のレビュー責任、監査ログを明文化
- 効果測定は“速度×品質”で:工数だけでなく、手戻り率・障害件数・MTTRなども併せて見る
2025年の「AI×システム開発」は、生成AIの導入競争から、開発の型(プロセス・知識・ガバナンス)をどう作るかの競争へ移りました。ソニー銀行のように、AIを中核に据えた開発エコシステムを設計できた組織ほど、スピードと品質の両取りが現実になると言えるでしょう。
AI利用について
本記事はAIツールの支援を受けて作成されております。 内容は人間によって確認および編集しておりますが、詳細につきましてはこちらをご確認ください。